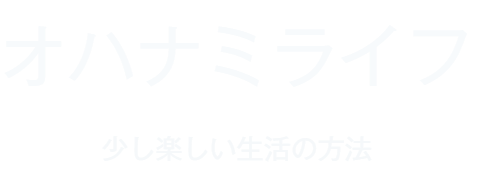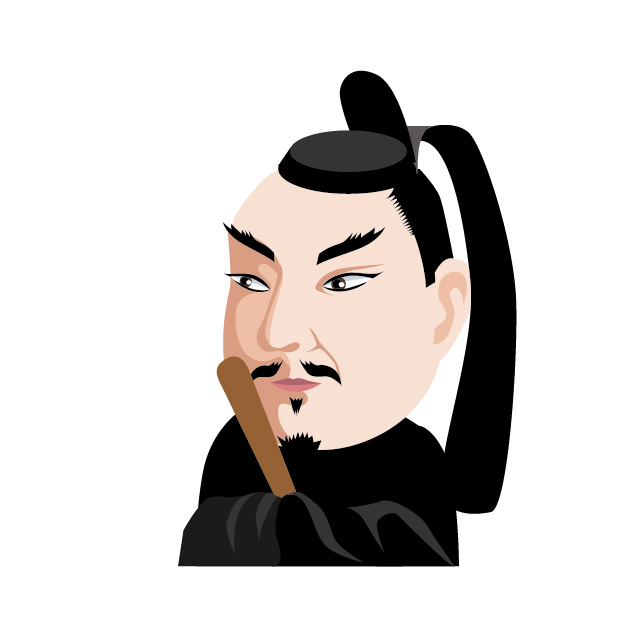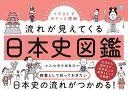江戸幕府の3代将軍 徳川家光が何をしたかを簡単に解説
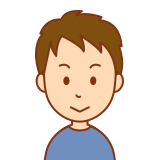
- 徳川家光って何をしたの?
- 何がすごかったの?
- 参勤交代って?
- 鎖国って?


年表
| いつ | できごと |
|---|---|
| 1623年 | 2代・秀忠の子である家光が征夷大将軍となる |
| 1627年 | 紫衣事件(しえじけん)が起こり、後水尾天皇の勅許を幕府が取り消す |
| 1635年 | 参勤交代が制度化され、幕藩体制がさらに強化される |
| 1635年 | 朱印船貿易を停止し、日本人の海外渡航も禁止 |
| 1637年 | 島原、唐津藩で島原の乱が起こり、翌年鎮圧される |
| 1639年 | ポルトガル船の渡航を禁止し、鎖国体制がほぼ完成 |
| 1641年 | オランダ商館を長崎の出島に移し、鎖国体制を強化 |
3代に渡り完成させた泰平の江戸時代
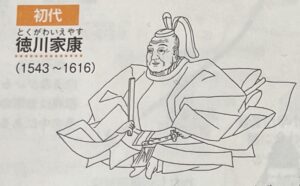
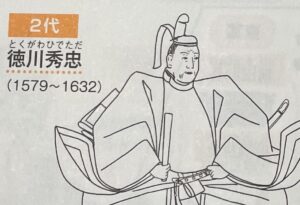
1623年に徳川家光は江戸幕府3代将軍に就任した。家康、秀忠が2代にわたり築き上げた江戸幕府の仕組みは、家光の時代に完成した。鎖国や参勤交代制度の実施、大城郭だった江戸城の完成など、江戸幕府の権威は不動のものになっていき、泰平の江戸時代が始まった。
鎖国までのプロセス

2代 秀忠時代
- 1612年 禁教令の発布
1614年にはキリスト教徒約300人が国外追放される。 - 1622年 元和の大殉教
長崎で55人のキリスト教徒が処刑される
3代 家光時代
- 1637年 島原の乱
キリスト教徒への弾圧に対する、教徒と農民の反乱 (天草四郎) - 1639年 ポルトガル船の来航禁止
鎖国といっても4つの外交窓口が存在した

鎖国といっても、じつは4つの外交窓口は開いていた。「鎖国」という言葉自体は19世紀にできたもの。
薩摩
薩摩藩が琉球との貿易窓口となっており、薩摩藩は琉球を通じて密貿易を行い、利益をあげていたという。
長崎
幕府の直轄領として、中国、オランダとの貿易を行っており、西洋学問や技術の輸入の窓口として繁栄した。
対馬
対馬藩では朝鮮との貿易を行っており、朝鮮王朝からは江戸時代に12回の通信使が派遣されていた。
松前
アイヌ民族をはじめ北方との交易が許されており、昆布、鮭などの海産物や、熊皮、ラッコの皮などが取引された。
鎖国の背景と鎖国が与えた後世への影響
鎖国の背景
鎖国政策が厳しくなった背景には、キリスト教の弾圧があった。西洋から伝わってくる、キリスト教の思想や信仰の排除が、幕府を鎖国という結論にいたらせた。
鎖国が与えた影響
鎖国がはじまると、西洋の文化の輸入や取り扱いが厳しくなっていった。そのため、日本は少しずつ世界情勢から取り残されていくことになっていった。その半面、鎖国の間は平和が続き、日本独自の文化が花開いた。しかし、幕末に諸外国が再び交易を求めてやってきたとき、その国力の差を痛感し、日本国内で革命が起き、その後は反動のように今度は急激な西洋化が進んだ。
参勤交代制度のはじまり
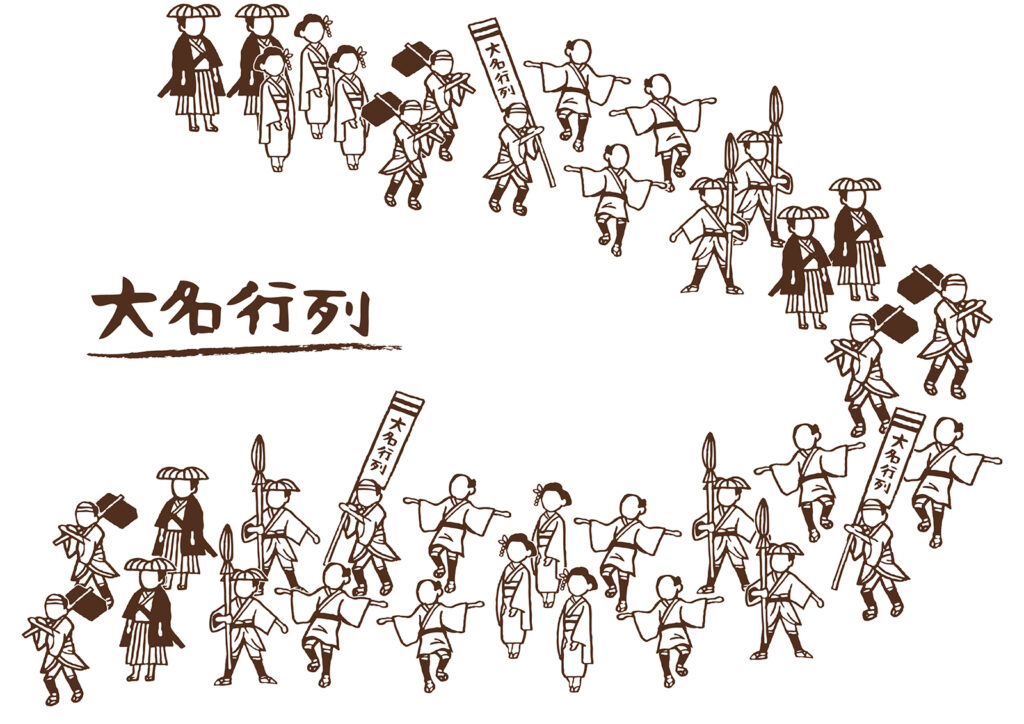
江戸の屋敷に住む大名
家康の時代、多くの諸大名は江戸に出向いていたが、家康の命により、大名達は江戸に屋敷を構え、そこに住むようになった。なかには、忠誠を誓うために、みずから人質を差し出す者もいたという。
武家諸法度の改訂で参勤交代が制度化
家光は、幕府への忠誠を誓わせることと、軍事に費用をかけて諸藩が力をつけることをさけるため、参勤交代を制度化した。1635年(寛永12年)諸大名統制の根幹となる法「武家諸法度」が改訂され、参勤交代制が明記された。このときは外様大名(関ヶ原の戦い後に徳川家に臣従した大名のこと)のみが対象だった。すべての大名に江戸への参勤が義務付けられるのは、1642年(寛永19年)になってから。
参勤交代のしくみ
前提ルール
- 大名の正室と嫡子は江戸に住む必要がある。
- 幕府へ人質を差し出すことで、忠誠を誓う
- 嫡子にはうまれた国元ではなく、江戸で物事を見る目を養わせる目的もある
期間
- 参勤交代を行なう時期は、大名により偶数年に参勤、奇数年に参勤で異なる
特別ルールとして、江戸に近い関東の大名は、半年ごと、遠方の対馬藩は3年に1度、蝦夷地の松前藩は6年に1度 - 江戸の在住期間は、原則1年
毎年、全国の約半数にあたる大名が江戸に在住 - 例外として、江戸常住の水戸藩、老中、若年寄(わかどしより)などの役職の者は、参勤交代の義務はない
人員・持ち物
- 参勤交代は、将軍への軍役奉仕と言う名目となり、大名行列も軍事形式を採って石高別に人数変動(騎馬武者、足軽、従者)基準はあっても大名が権威を誇示するために、大人数を引き連れてくる
- 行列の先頭は「先払い」が往来する人々を制し、「先箱」(正装が入れられた箱持ち)、「槍持ち」、「徒士」(下級武士)と続き、その後ろに「鉄砲隊」、「槍隊」などが続く。
藩主は駕籠(かご)に乗り、側近が駕籠脇としてその周りを囲んで警護 - 生活用品として「乗り換え用の馬」、「雨具」、「茶弁当」、「漬け物樽」、「風呂」、「トイレ」、「ろうそく」、娯楽として「囲碁」や「将棋」なども運ぶ。
- 食事は、毒殺を防ぐためにお付きの料理人が持参の料理道具で用意する。食材のほとんどは旅先の土地で採れる野菜などを使うが、「米」、「水」、「塩」、「醤油」などは樽にいれて国元から運ぶ
宿泊
- 参勤交代の大名が宿泊する宿場町の施設を「本陣」という
- 人数が多くて本陣だけでは足りない場合は、予備の宿「脇本陣」に宿泊
- 本陣への宿泊は相応の身分が必要だが、脇本陣は一般庶民も宿泊可能
- 宿場町には、本陣が2~3つある
- 大名行列の宿泊は、前もって「先触」(さきぶれ)と言う書状により伝達される
- 伝達されると約3ヵ月前から準備を開始し、行列が到着すると、本陣の前に「宿役人」、「町名主」、「町年寄」など関係者が正装で出迎える
町民のルール
- 街道で大名行列に出会ったら、一般の大名行列の際は、通行の邪魔にならないように道の端へ寄る
土下座して迎えるのは一般的に将軍や徳川御三家の行列が来たときだけ - 大名行列の前を横切ったり、列を乱したりすることは原則禁止
ただし、書状などを運ぶ飛脚や産婆に限っては、行列を横切ることが許される - 大名行列が集中する江戸城面前では、待つ時間が長すぎるのため救済措置として、行列に「一ノ切り」や「二ノ切り」と言う道幅ほどの切れ目を作ることで、町民が自由に往来できるようにする
参勤交代がもたらした効果
諸藩にとって参勤交代は大きな負担となった。その一方で、参勤交代で江戸に来た人々が、江戸の流行を故郷に持ち帰り、さまざまな文化が日本全国に広まるきっかけになった。また街道が整備され、宿場町が栄える効果もあった。
武断政治と浪人
武断政治
武断政治とは、戦国時代の風習を受け継いだ政治で、武力や権力を背景に政治を行うこと。家光の世は武断政治の時代で、ルールに厳しく、違反した藩は厳しく罰せられ、時には大名家が取り潰されることもあった。
浪人の大量発生
幕府のルールを破った場合には領地の没収や、雇用切りを命じ大名家の家臣をやめさせる処罰があり、雇い主をなくした家臣たちが浪人となる事案が大量に発生し、社会問題となった。
あとがき
学校の授業で覚えさせられた鎖国や参勤交代制度だが、仕組みなどを改めてみるとよく考えられていておもしろい。鎖国は一時的にはうまくいったようだが、幕末にはその反動がやってくる。参勤交代は江戸に定期的に来させることで街道の整備や繁栄、文化の全国への広まりなど良い効果もあったのが、これも計算していたらかなり優秀だったと思う。
ではまた、ごきげんよう。