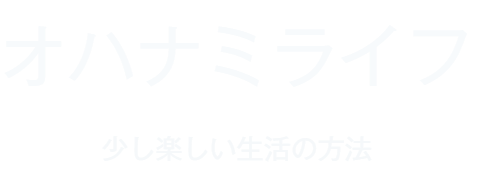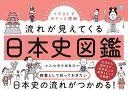ペリーの来航から5年後、大老・井伊直弼は勅許のないまま日米修好通商条約の締結に踏み切る。
これが多方面から大バッシングを受けた。
さらに、14代将軍の座をめぐる将軍継嗣問題が起こった。
その井伊直弼について「井伊直弼はどのように大老になった」「井伊直弼の安政の大獄とは」「桜田門外の変とは」が気になる。
また、「14代将軍をめぐる将軍継嗣問題とは」についても学んでいきたい。
そこで、今回の内容はこちら
- 井伊直弼はどのように大老になったか
- 14代将軍をめぐる将軍継嗣問題とは?
- 井伊直弼の安政の大獄とは?
- 桜田門外の変とは?

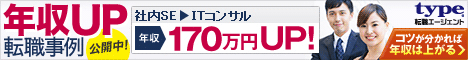
年表
| いつ | できごと |
|---|---|
| 1858年 | 井伊直弼が大老に就任し、将軍継嗣問題は南紀派が優勢となる |
| 1858年 | 大老・井伊が、勅許を得ずに日米修好通商条約を締結 |
| 1858年 | 13代・家定が死去。 徳川慶福が14代・家茂として将軍となる |
| 1858年 | 一橋派や攘夷派を弾圧する安政の大獄がはじまる |
| 1859年 | 諸外国との条約締結により、横浜、長崎、箱館が開港する |
| 1860年 | 勝海舟、福沢諭吉らを乗せた咸臨丸が、太平洋を横断する |
| 1860年 | 水戸浪士を中心とする一派が井伊直弼を暗殺(桜田門外の変) |

井伊直弼はどのように大老になったか
14男の井伊直弼は出世に縁遠い存在だった。
勉強のかたわらに茶道や歌、鼓(つづみ)などをやりながら日々を送っていた。
あだ名は「ちゃかぼん」”ちゃ”は”茶”、”か”は”歌”、”ぼん”は鼓の音、だった。
しかし、36歳の時、彦根藩主を継ぐことになり、13代・家定にも認められて44歳で江戸幕府の大老に就任した。

14代将軍をめぐる将軍継嗣問題とは?
13代・家定のあとの14代将軍をめぐり、南紀派と一橋派が対立した。
井伊直弼が大老となることで南紀派が力を増し、徳川慶福が14代・家茂となった。
南紀派
井伊直弼をはじめとする、譜代大名や将軍の側近、幕臣、大奥の女性などが中心の勢力。
紀州藩主・徳川慶福を推す。
一橋派
幕府から排除されていた、越前福井藩や薩摩藩など、有力大名たちを中心とする勢力。
徳川斉昭の子・徳川(一橋)慶喜を推す。
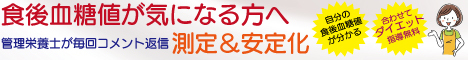
井伊直弼の安政の大獄とは?

日米修好通商条約の調印
ペリー来航を受けて、いよいよ鎖国を続けられなくなった日本は、諸外国との交戦の可能性も視野に入れて動かなくてはならなかった。
朝廷は日米修好通商条約の締結に難色を示した。
しかし、井伊直弼は拒否することで戦争(諸外国が武力行使してくる)になることを警戒し、大老として独断で条約に調印した。
攘夷派・尊王派の激怒
この条約締結に対して、攘夷派や尊王派は激怒した。
天皇の意向を無視して諸外国に屈したと評価をし、幕府への不満を高めた。
安政の大獄による弾圧
こうして激しくなる幕府への批判に対し、井伊直弼は弾圧をはじめた。
譲位を決行しようとする前水戸藩主の徳川斉昭や、その子・一橋慶喜に蟄居(ちっきょ)を命じ、幕府批判を行う学者らを処刑する安政の大獄を行った。

桜田門外の変とは?

安政の大獄で、長州藩士・吉田松陰ら、多くの思想家や学者が処刑された。
弾圧の中で、尊王攘夷派の志士たちは同士の仇を討つべく、大老・井伊直弼の暗殺を計画するようになった。
そして、水戸藩の浪士たちを中心とした桜田門外の変で、大老・井伊直弼は暗殺された。

まとめ
今回の内容をまとめると
- 井伊直弼は36歳で彦根藩主を継ぎ、13代・家定にも認められ、44歳で江戸幕府の大老に就任した。
- 14代将軍をめぐり、南紀派と一橋派が対立していたが、井伊直弼が大老になることで南紀派が力を増し徳川慶福が14代・家茂となった。
- 井伊直弼は大老として朝廷の勅許なしで日米修好通商条約の調印を行い、攘夷派や尊王派は激怒した。その幕府批判に対して井伊直弼は安政の大獄で弾圧を行った。
- 安政の大獄の中で、尊王攘夷派の志士たちは同士の仇を討つべく、大老・井伊直弼の暗殺を計画するようになり、水戸藩浪士を中心とした桜田門外の変で井伊直弼は暗殺された。
ではまた、ごきげんよう。