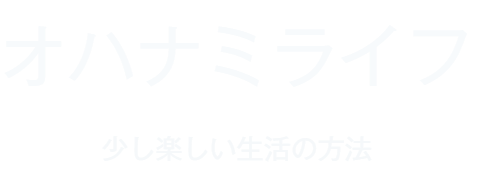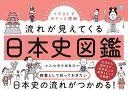皇位継承をめぐる争いから鎌倉幕府が滅亡し、南北朝の争いの中から室町幕府が開かれる
改めてわかったのが、足利尊氏の立ち回りがすごい。潮目を読んでサバイブして成りあがる能力がすごいと感じる。鎌倉幕府としては問題山積みの中で朝廷に意見をもとめられ、その回答の結果、的に回すことになったことと足利尊氏、新田義貞の裏切りで滅亡してしまう悲劇ともいえる。
ポイント
- 朝廷分裂の内容とは
- 北条氏の対応は
- 後醍醐天皇が挙兵
- 足利尊氏の裏切り
- 鎌倉幕府はどうやって滅びた
- 室町幕府のはじまり
- 足利尊氏の立ち回り
- 南北朝とは
年表
| いつ | できごと |
|---|---|
| 1318年 | 後醍醐天皇即位。院制廃止 |
| 1331年 | 後醍醐天皇楠木正成が挙兵する元弘の変が起こる |
| 1332年 | 後醍醐天皇、隠岐に流される。護良親王挙兵 |
| 1333年 | 後醍醐天皇、隠岐を脱出。鎌倉幕府が滅ぼされる |
| 1335年 | 足利尊氏が建武政権から離反する |
| 1336年 | 後醍醐天皇、吉野に逃れ南朝をたてる |
| 1338年 | 足利尊氏、北朝から征夷大将軍に任命される |
| 1339年 | 後醍醐天皇、吉野で亡くなる |
おもな登場人物
皇位継承の争い
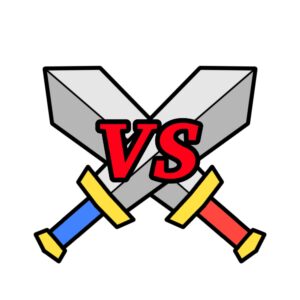
13世紀後半、朝廷は大覚寺統(南朝)と持明院統(北朝)の二派にわかれ、皇位継承をめぐる争いをした。鎌倉幕府はこれに介入し、両派から交代で天皇を出す方法を提案した。
後醍醐天皇の挙兵

幕府の皇位継承介入を不快に思った後醍醐天皇は、即位後、政権を幕府から朝廷に取り戻すため、倒幕を決意し、挙兵するが、失敗。隠岐に流される。
護良親王の救出

皇子の護良親王や悪党の楠木正成らが畿内の悪党をまとめ、反幕府の動きを活発化させ、後醍醐天皇を助けようと一致団結する。
反幕府勢力討伐の命令

対する鎌倉幕府は御家人筆頭の足利高氏(のちの尊氏)を京都に派遣、反幕府勢力の討伐を命令する。しかし、14代執権・北条高時の政治に不満のあった高氏は幕府を裏切り、逆に幕府の出先機関である六波羅探題を攻め落とす。
鎌倉幕府の滅亡

同じころ、関東の有力御家人・新田義貞も後醍醐天皇につくことを決意。関東の御家人たちも新田を支持し、大軍となって鎌倉を攻めた。これにより北条高時以下、北条一門は滅ぼされ、150年続いた鎌倉幕府は滅亡、南北朝時代に突入した。
鎌倉幕府滅亡まで続いた源平合戦
足利尊氏は、鎌倉幕府を開いた源頼朝の血統が途絶えたあと、源氏の棟梁とされた名門の出身。また鎌倉幕府倒幕の立役者である新田義貞も源氏の名門だった。対する北条氏は平氏の系譜。このことから尊氏も、義貞も、源氏が興した鎌倉幕府を北条氏が握っていたことに不満があったともいわれている。
建武の新政

後醍醐天皇は建武の新政と呼ばれる天皇中心の政治をはじめた。しかし、全国の土地の所有権をすべて後醍醐天皇が確認するなど、天皇の権力を絶対的に強めたため社会は混乱。恩賞も公家を優先し、武士の不満が高まった。
室町幕府

建武の新政が社会の混乱を招くと判断した足利尊氏は、後醍醐天皇に反旗をひるがえす。持明院統(北朝)から光明天皇をたて、政治の方針を示す建武式目を制定。京都に室町幕府を開いた。
皇統が分断

足利尊氏がたてた光明天皇がいる京都の北朝に対して、後醍醐天皇は吉野(奈良県)にながれて南朝を開き、60年続く南北朝時代がはじまった。
あとがき
日本史の流れを大まかに学ぶことで、人物名や年号を覚えることでどこかつまらないと感じていた歴史をもっと楽しく学べると思う。
ではまた、ごきげんよう。